36th ACFE Global Conference : 2日目
2025年6月26日36th ACFE本部カンファレンス総括
2025年7月9日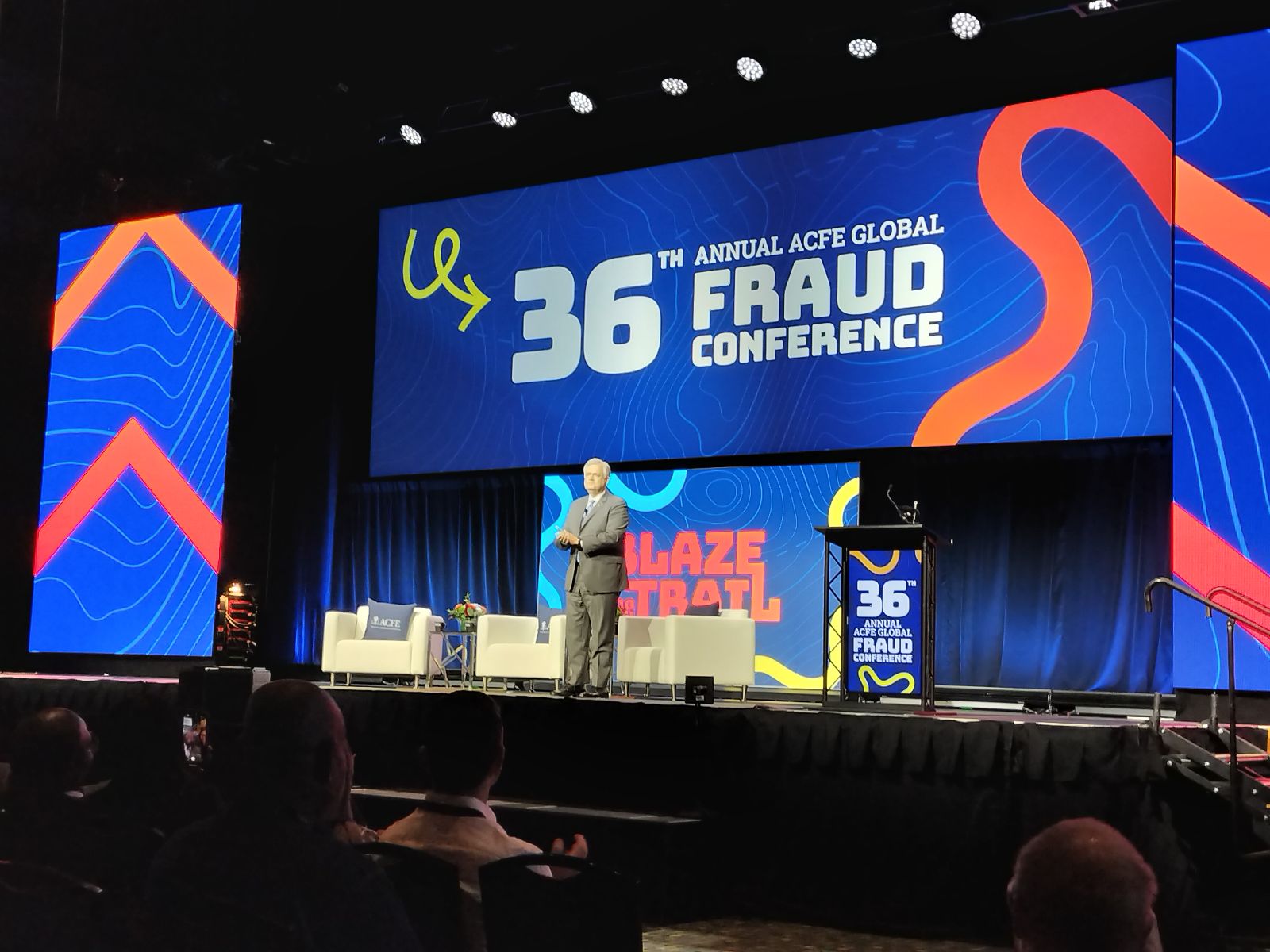
ACFE GLOBAL FRAUD CONFERENCE
第36回Annual ACFE Global Fraud Conference 現地レポート 3日目:ACFE JAPAN 事務局
日時:2025年6月22日(日)~27日(金)(日本時間)
場所:テネシー州ナッシュビル
3 日目 トピック(2025年6 月 25 日 水曜日)

朝食会場
3日目の今日は本カンファレンスの最終日です。朝食に集まった参加者の中にはスーツケースを携えている人も見られ、参加者同士で名残を惜しむなど、慌ただしい雰囲気に包まれていました。
本セッションでは、ACFE会長のジョン・ギル氏によるインタビュー形式で、米大手通信企業MCIでの不正の現場で何が起きていたのか、そして、数百万ドル規模の不正を主導したウォルター・パブロ氏が、出所後に得た教訓は何であったのか、その動機、手口、葛藤、そして終焉と、自身の実体験をユーモアを交えつつ、赤裸々に語りました。
午前:分科会①
午前の分科会では、2004年に初めてACFEグローバルカンファレンスに登壇して以来20年ぶりに、ある人物が再登壇しました。その人物とは、詐欺加害者としての実体験を語り続けてきた、元“詐欺師(フロードスター)”のウォルト・パブロ氏です。本セッションでは、ACFE会長のジョン・ギル氏によるインタビュー形式で、米大手通信企業MCIでの不正の現場で何が起きていたのか、そして、数百万ドル規模の不正を主導したウォルター・パブロ氏が、出所後に得た教訓は何であったのか、その動機、手口、葛藤、そして終焉と、自身の実体験をユーモアを交えつつ、赤裸々に語りました。
パブロ氏はかつて、通信大手MCI/ワールドコム社において、財務報告詐欺および横領行為を主導し、自身でも600万ドルを不正に取得したとして有罪判決を受けました。この事件は、同社の巨額破綻(当時全米最大規模)につながる深刻な不正会計の一端とされています。
セッションでは、ギル会長の問いに導かれ、パブロ氏はユーモアを織り交ぜながら、まず、当時の社内文化としてや上層部からの圧力、目標未達への恐れ、業績至上主義が、いかにして社員の倫理的判断を鈍らせたかについて語りました。
氏は、かつて所属していたMCIにおいて、創業者のバーニー(バーナード)・エバーズ氏らのリーダーシップに感銘を受けつつも、次第にその“成果至上主義”に疑問を抱くようになったといいます。
パブロ氏は、会社の急成長とそれに伴うプレッシャーが、倫理観を麻痺させたと指摘します。「倫理規定なんて見たこともなかった。オフィスに貼ってあったのはロゴと株価だけ。そんな中で“数字を動かす”ことが正義になっていた」
セッションでは、ギル会長の問いに導かれ、パブロ氏はユーモアを織り交ぜながら、まず、当時の社内文化としてや上層部からの圧力、目標未達への恐れ、業績至上主義が、いかにして社員の倫理的判断を鈍らせたかについて語りました。
氏は、かつて所属していたMCIにおいて、創業者のバーニー(バーナード)・エバーズ氏らのリーダーシップに感銘を受けつつも、次第にその“成果至上主義”に疑問を抱くようになったといいます。
パブロ氏は、会社の急成長とそれに伴うプレッシャーが、倫理観を麻痺させたと指摘します。「倫理規定なんて見たこともなかった。オフィスに貼ってあったのはロゴと株価だけ。そんな中で“数字を動かす”ことが正義になっていた」

ウォルト・パブロ氏とギル会長
さらには、業績の悪化について「ヘルプが必要」と呼びかける上司の言葉も、結果的に部下に対し不正を“協力”と錯覚させる空気を醸成していたといいます。「周囲が“これくらいならOK”というムードをつくっていた」と、上司や同僚が積極的に不正に関与するわけではないものの、「暗黙の了解」として危うい行動が許容されることで、若手の判断基準が揺らいでいく様子が語られました。
「同僚もやっている」「一時的な帳尻合わせだ」「会社のためになる」という誤った正当化や大義名分といった要素は、今日の企業環境でも繰り返されるリスクであるとし、経営層における倫理的リーダーシップの不在が、不正の土壌を生み出すと指摘しました。
「2〜2.5億ドルが動く世界で、次第に組織の腐敗に野望をいだくようになり、自分も取り分を得るべきだと考えるようになった」と語るパブロ氏は、企業文化と業界構造そのものに対する失望から、外部の共犯者と手を組み、「900番通話サービス」(注:日本でいうかつてのダイヤルQ2にような有料情報サービス)事業者を標的とした不正スキームを開始。MCIに200万ドルの債務を負っていたアダルト系サービス事業者に対し、「支払いがなければ即時回線停止」と脅した上で、共犯者を“エンジェル投資家”に仕立て上げ、債務を肩代わりするという偽装取引を演出しました。
この手法により、MCIには架空の債権回収を報告しつつ、実際の資金はケイマン諸島の口座へ送金。当初こそ一部支払った形を装ったものの、徐々に債務全額を帳消しとするようになり、最終的には複数事業者から半年間で合計600万ドルを詐取したといいます。
「誰に迷惑がかかるのか?相手は反社会的ビジネスを営む者だからこれでいいのだ、という歪んだ正当化が、自らの罪悪感を鈍らせた」とパブロ氏は述懐します。
当時の会計処理は紙ベースで、複数の監査機能が欠如しており、自分が督促し、入金されたことにして、そのまま帳消しにできたという、まさに“職務の分離”がなされていなかった典型例だと語りました。
不正スキームの拡大により、社外の営業担当者が「自分のクライアントにも融資してほしい」と接触してきたことで、氏は「これはもはや制御不能だ」と悟り、終了を決断。しかし数ヶ月後、上司から「会計処理の一部に関する問い合わせがある」と告げられたとき、全てが終わる予感がしたといいます。
「最初は弁護士にも『自分は無関係だ』と言い張っていた。しかし“ケイマン諸島”という言葉が出た瞬間、全てが崩れたのです」
「同僚もやっている」「一時的な帳尻合わせだ」「会社のためになる」という誤った正当化や大義名分といった要素は、今日の企業環境でも繰り返されるリスクであるとし、経営層における倫理的リーダーシップの不在が、不正の土壌を生み出すと指摘しました。
「2〜2.5億ドルが動く世界で、次第に組織の腐敗に野望をいだくようになり、自分も取り分を得るべきだと考えるようになった」と語るパブロ氏は、企業文化と業界構造そのものに対する失望から、外部の共犯者と手を組み、「900番通話サービス」(注:日本でいうかつてのダイヤルQ2にような有料情報サービス)事業者を標的とした不正スキームを開始。MCIに200万ドルの債務を負っていたアダルト系サービス事業者に対し、「支払いがなければ即時回線停止」と脅した上で、共犯者を“エンジェル投資家”に仕立て上げ、債務を肩代わりするという偽装取引を演出しました。
この手法により、MCIには架空の債権回収を報告しつつ、実際の資金はケイマン諸島の口座へ送金。当初こそ一部支払った形を装ったものの、徐々に債務全額を帳消しとするようになり、最終的には複数事業者から半年間で合計600万ドルを詐取したといいます。
「誰に迷惑がかかるのか?相手は反社会的ビジネスを営む者だからこれでいいのだ、という歪んだ正当化が、自らの罪悪感を鈍らせた」とパブロ氏は述懐します。
当時の会計処理は紙ベースで、複数の監査機能が欠如しており、自分が督促し、入金されたことにして、そのまま帳消しにできたという、まさに“職務の分離”がなされていなかった典型例だと語りました。
不正スキームの拡大により、社外の営業担当者が「自分のクライアントにも融資してほしい」と接触してきたことで、氏は「これはもはや制御不能だ」と悟り、終了を決断。しかし数ヶ月後、上司から「会計処理の一部に関する問い合わせがある」と告げられたとき、全てが終わる予感がしたといいます。
「最初は弁護士にも『自分は無関係だ』と言い張っていた。しかし“ケイマン諸島”という言葉が出た瞬間、全てが崩れたのです」
司法当局が動いたのは発覚から約1年後。その間、パブロ氏は閉鎖的な生活を送り、民事訴訟と刑事訴追の両方に備える精神的苦悩と向き合うことになります。
パブロ氏は最終的に、41か月(約3年半)の実刑判決を受け、米南部の複数の刑務所で服役することになります。服役中は、図書館業務や読書指導に従事しながら、将来について思索を深める日々を送ったといいます。かつて映画『インフォーマント!』のモデルとなったマーク・ウィテカー氏と同室だったエピソードも紹介され、刑務所内での人間関係が語られました。
2003年から2004年頃に出所した彼は、「おかえりなさい」の言葉とともに更生施設に送られ、仕事もなく、家族との関係も複雑な中で新たな人生を模索することになったといいます。当時6歳と8歳だった子どもたちは、彼が不正に関与していた年齢に達し、責任の重さを改めて感じたそうです。
パブロ氏は最終的に、41か月(約3年半)の実刑判決を受け、米南部の複数の刑務所で服役することになります。服役中は、図書館業務や読書指導に従事しながら、将来について思索を深める日々を送ったといいます。かつて映画『インフォーマント!』のモデルとなったマーク・ウィテカー氏と同室だったエピソードも紹介され、刑務所内での人間関係が語られました。
2003年から2004年頃に出所した彼は、「おかえりなさい」の言葉とともに更生施設に送られ、仕事もなく、家族との関係も複雑な中で新たな人生を模索することになったといいます。当時6歳と8歳だった子どもたちは、彼が不正に関与していた年齢に達し、責任の重さを改めて感じたそうです。

転機となったのは、ACFE元会長のジム(ジェームス)・ラトリー氏との出会いだったといいます。ラトリー氏の支援により、400人の米国連邦検事の前で講演する機会が与えられ、「最も怖い経験のひとつだった」とのことですが、そこから講演活動が本格化したそうです。
不正の過程で「どこまでが許容され、どこからが犯罪なのか」という判断を自ら麻痺させていた過去を振り返りながら、氏は今、「倫理の教育と職場文化の重要性を訴える立場」として再起の道を歩んでいます。
現在、「Prisonology」というコンサルティング会社を経営しており、元連邦刑務所職員らとともに、受刑者支援や法廷提出用の鑑定意見書作成などを行っており、クライアントの中には、有名事件に関与した人物も含まれているとのことです。
将来的には「再び講演活動にも力を入れたい」としつつ、Prisonologyを通じた刑務所制度改革や政策支援にも引き続き関与していく予定だという。すでに本の執筆歴がある彼は、もう一冊書くかはわからないが、ホワイトカラー犯罪とその背景にある人間心理を、もっと伝えていきたい、と啓蒙活動に意欲的でした。
この対談は、「個人の倫理観の欠如」だけでは説明できない組織的不正の構造を浮き彫りにしています。トップの姿勢、昇進制度、倫理教育、そして“空気”──。これら全てが社員一人ひとりの判断に影響を与え、正しい行動を見失う可能性があることを、パブロ氏の証言は如実に物語っています。
企業文化、内部統制、倫理観の重要性が改めて浮き彫りになり、CFEや企業リスク管理者にとっても示唆深い内容のセッションでした。
講演の後半では、元FBI捜査官や元連邦検察官を含む来場者からの、捜査・起訴時の経験や企業文化、個人の価値観の変容など多岐にわたる、実務的な質問が寄せられました。 当時(2000年代初頭)はまだ捜査も今ほど厳格ではなく、召喚状も「協力を求める手紙」程度だったが、今では家宅捜索や逮捕に発展することもあり、取り締まりは格段に厳しくなっていること、そして、フランク・アバグネイル氏(映画『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』のモデル)との会話で「君のような人間はひとりでやっていくしかない」と言われたこと、また、「自分に好かれたい、期待に応えたい」という心理を利用する形で若い部下が不正に巻き込まれたことに対する自責の念など、の回答が印象的でした。
不正の過程で「どこまでが許容され、どこからが犯罪なのか」という判断を自ら麻痺させていた過去を振り返りながら、氏は今、「倫理の教育と職場文化の重要性を訴える立場」として再起の道を歩んでいます。
現在、「Prisonology」というコンサルティング会社を経営しており、元連邦刑務所職員らとともに、受刑者支援や法廷提出用の鑑定意見書作成などを行っており、クライアントの中には、有名事件に関与した人物も含まれているとのことです。
将来的には「再び講演活動にも力を入れたい」としつつ、Prisonologyを通じた刑務所制度改革や政策支援にも引き続き関与していく予定だという。すでに本の執筆歴がある彼は、もう一冊書くかはわからないが、ホワイトカラー犯罪とその背景にある人間心理を、もっと伝えていきたい、と啓蒙活動に意欲的でした。
この対談は、「個人の倫理観の欠如」だけでは説明できない組織的不正の構造を浮き彫りにしています。トップの姿勢、昇進制度、倫理教育、そして“空気”──。これら全てが社員一人ひとりの判断に影響を与え、正しい行動を見失う可能性があることを、パブロ氏の証言は如実に物語っています。
企業文化、内部統制、倫理観の重要性が改めて浮き彫りになり、CFEや企業リスク管理者にとっても示唆深い内容のセッションでした。
講演の後半では、元FBI捜査官や元連邦検察官を含む来場者からの、捜査・起訴時の経験や企業文化、個人の価値観の変容など多岐にわたる、実務的な質問が寄せられました。 当時(2000年代初頭)はまだ捜査も今ほど厳格ではなく、召喚状も「協力を求める手紙」程度だったが、今では家宅捜索や逮捕に発展することもあり、取り締まりは格段に厳しくなっていること、そして、フランク・アバグネイル氏(映画『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』のモデル)との会話で「君のような人間はひとりでやっていくしかない」と言われたこと、また、「自分に好かれたい、期待に応えたい」という心理を利用する形で若い部下が不正に巻き込まれたことに対する自責の念など、の回答が印象的でした。
午前:分科会②
続く分科会では、「爆発的に増加する不正に立ち向かうための、調査チームの強化策とは」を聴講しました。講師は、ドラ・ゴメス 氏(CFE, CRMA/EY ファイナンシャルクライム・コンプライアンス部門 マネージャー)とリチャード・ヴィタール氏(CFE/Valley National Bank 調査部門責任者)です。本セッションでは、急増する不正行為に対応できる「実戦的かつ柔軟な不正対策チーム」をいかに構築するかについて、実例を交えながら紹介されました。EYのゴメス氏とValley National Bankのヴィタール氏の両名は、業界の最前線で数々の調査を指揮してきた実務家であり、実装可能な組織設計・人材開発・テクノロジー活用の要点が具体的に提示されました。

ゴメス氏は、サイロ化された部門構造が不正リスクの温床になっていると警鐘を鳴らしました。不正リスク管理、監査、内部通報、コンプライアンス、ITセキュリティなどが連携して、初めて早期発見と抑止が可能になると強調します。そのうえで、各部門が共通認識をもってリスクを可視化できる「統一フレームワーク」構築の必要性が訴えられました。
ヴィタール氏は、「初動対応」と「調査」の役割分担の明確化を挙げ、効果的な組織設計を解説しました。例として、「アラート対応チーム」は日々のモニタリングと検知ツール対応をし、「調査チーム」は潜在的リスクや重大案件の実地調査・インタビュー・証拠保全を行う、という枠組みを提案し、これにより、迅速な対応と精緻な調査の両立が可能となり、不正対応力が飛躍的に高まると説明しました。
ヴィタール氏は、「初動対応」と「調査」の役割分担の明確化を挙げ、効果的な組織設計を解説しました。例として、「アラート対応チーム」は日々のモニタリングと検知ツール対応をし、「調査チーム」は潜在的リスクや重大案件の実地調査・インタビュー・証拠保全を行う、という枠組みを提案し、これにより、迅速な対応と精緻な調査の両立が可能となり、不正対応力が飛躍的に高まると説明しました。
さらに、両氏とも、AIやマシンラーニング(ML)による不正検知強化の有効性を認めつつも、「過信は禁物」と警鐘を鳴らしました。AIが示す“シグナル”に対し、人間の経験・倫理・判断力で背景を読み解くプロセスが不可欠であり、調査担当者のスキルセット向上が並行して求められると述べました。
重要なポイントとして、両氏は以下を強調しました。
●「情報を共有できる文化」をいかに醸成するかが初動対応の鍵
● アラート担当と調査担当の機能分離・連携設計が、不正対応チームを最適化する
● フィードバックループ(分析結果→施策改善→再分析)を意図的に設計することで、組織のリスク感度が上がる
● 不正チームの持続的成長には、実戦に即した教育・訓練体制が不可欠
今後の展望と推奨アクションとして、以下を提示しました。
1. 不正リスクに対応するチーム構成を定期的に見直す
2. テクノロジーを導入する際は、業務設計・人材の成熟度との整合性を確認する
3. 全社的な“アンチフロード”文化醸成のために、部門を超えた定例連携を制度化する
このセッションは、現場実務と戦略設計の両輪の見直しの重要性について考える機会となりました。急増する不正に組織としてどう備えるか、そのヒントが詰まったセッションでした。
重要なポイントとして、両氏は以下を強調しました。
●「情報を共有できる文化」をいかに醸成するかが初動対応の鍵
● アラート担当と調査担当の機能分離・連携設計が、不正対応チームを最適化する
● フィードバックループ(分析結果→施策改善→再分析)を意図的に設計することで、組織のリスク感度が上がる
● 不正チームの持続的成長には、実戦に即した教育・訓練体制が不可欠
今後の展望と推奨アクションとして、以下を提示しました。
1. 不正リスクに対応するチーム構成を定期的に見直す
2. テクノロジーを導入する際は、業務設計・人材の成熟度との整合性を確認する
3. 全社的な“アンチフロード”文化醸成のために、部門を超えた定例連携を制度化する
このセッションは、現場実務と戦略設計の両輪の見直しの重要性について考える機会となりました。急増する不正に組織としてどう備えるか、そのヒントが詰まったセッションでした。
午後:基調講演
3日目午後の基調講演は、本会最後となる、クロージング・ジェネラル・セッションです。
まず、ジョン・ギル会長が、ACFEスタッフやスポンサー、他数多くの様々な人の尽力によって本カンファレンスが滞りなく行われたことに、感謝の意を述べました。
そして、来年の開催地として、アメリカ東部マサチューセッツ州のボストンであるとアナウンスがありました。
その後「 加害者と捜査官、それぞれの視点から見た国際金融詐欺事件」と銘打たれたこのセッションでは、極めて異色かつ示唆に富む対談が行われました。

ジョン・ギル会長
登壇したのは、かつて国際的な詐欺事件に関与し有罪判決を受けたアレックス・ジャリヴ氏と、その事件の捜査を主導した元FBI特別捜査官リチャード・ビーズリー氏。加害者と捜査官が同じ場に立ち、事件の舞台裏とそこから得られた教訓を語るという極めてユニークな形式でした。
ジャリヴ氏は、2000年代後半から2010年代初頭にかけて、米国の再生可能燃料制度(RINクレジット制度)を悪用した不正取引事件に関与したとされる人物です。氏を含む関係者らは、実際には流通していないバイオディーゼルの輸入・販売実績を偽装し、制度上発行可能なRINを不正に取得・販売することで、数千万ドル規模の不当な利益を得ていたとされています。
さらに、こうした犯罪収益を複数の国・企業を経由した複雑な金融取引を通じてマネーロンダリングしたともされています。その結果、2014年、3,700万ドルを超えるこのバイオディーゼル詐欺計画に関与したとして彼の父親ジェームス・ジャリヴとネイサン・ストリアーとともに有罪判決を受け、収監されました。
加害者の視点
アレックス・ジャリヴ氏は、華やかな経済環境の中で育ち、自宅には複数のナニーが常駐し、物質的には何不自由のない生活をしていたとまず語ります。家族との絆が薄く、11歳のときにはラスベガスの高級ホテルで友人が不審死を遂げるというショッキングな経験をしました。この事件を契機に、精神的な拠り所を失い、飲酒や薬物、非行へと傾倒していったといいます。
青年期にはミュージシャンを目指しましたが、夢は叶わず、20歳前後から父親とともにモーゲージ(住宅ローン)関連のビジネスに従事。しかし、その実態は、申告内容の改ざんや、架空取引を活用した詐欺スキームでした。「最初は“この業界ではこういうもの”という空気に流されていました」と語るアレックス氏。2008年の不動産バブル崩壊とともに旧事業は立ち行かなくなり、以後はタイムシェア詐欺やバイオディーゼル燃料を利用した補助金詐欺へと活動を移行しました。
ジャリヴ氏は、2000年代後半から2010年代初頭にかけて、米国の再生可能燃料制度(RINクレジット制度)を悪用した不正取引事件に関与したとされる人物です。氏を含む関係者らは、実際には流通していないバイオディーゼルの輸入・販売実績を偽装し、制度上発行可能なRINを不正に取得・販売することで、数千万ドル規模の不当な利益を得ていたとされています。
さらに、こうした犯罪収益を複数の国・企業を経由した複雑な金融取引を通じてマネーロンダリングしたともされています。その結果、2014年、3,700万ドルを超えるこのバイオディーゼル詐欺計画に関与したとして彼の父親ジェームス・ジャリヴとネイサン・ストリアーとともに有罪判決を受け、収監されました。
加害者の視点
アレックス・ジャリヴ氏は、華やかな経済環境の中で育ち、自宅には複数のナニーが常駐し、物質的には何不自由のない生活をしていたとまず語ります。家族との絆が薄く、11歳のときにはラスベガスの高級ホテルで友人が不審死を遂げるというショッキングな経験をしました。この事件を契機に、精神的な拠り所を失い、飲酒や薬物、非行へと傾倒していったといいます。
青年期にはミュージシャンを目指しましたが、夢は叶わず、20歳前後から父親とともにモーゲージ(住宅ローン)関連のビジネスに従事。しかし、その実態は、申告内容の改ざんや、架空取引を活用した詐欺スキームでした。「最初は“この業界ではこういうもの”という空気に流されていました」と語るアレックス氏。2008年の不動産バブル崩壊とともに旧事業は立ち行かなくなり、以後はタイムシェア詐欺やバイオディーゼル燃料を利用した補助金詐欺へと活動を移行しました。

会場の様子
特にバイオ燃料詐欺では、カナダにある精製所を買収し、架空の製造・輸送を装って、米国およびカナダの税制優遇措置から多額の補助金を不正取得。「施設の生産能力を過大に申告し、タンクローリーで偽装輸送を行って証拠を捏造していました」と明かしました。架空の原材料を米国から輸入したことにし、同じ燃料を繰り返し運ぶことで“生産・輸出・輸入”の実績を捏造していたといいます。
米国環境保護庁(EPA)のシステムに虚偽データを入力する役割も担っており、「当時は1週間に25万ドル規模の取引がありました。すべてが虚構で成り立っていた」と振り返りました。
タイムシェア詐欺では、被害者に「物件を売却できる」と持ちかけ、仲介手数料や税金名目で金銭を支払わせる“リロード”型の手法を展開。被害者が一度支払いを済ませた後も、「手続きに追加費用が必要」と再度の支払いを求める悪質な構造が構築されていました。
同氏は、「コールセンターでは、スタッフが泣き叫ぶ被害者に対しても冷酷に電話を切り、別名で再度架電するなどの指示が飛んでいました」と証言。顧客データベースは精緻に管理され、苦情が発生すると会社名や電話番号を変更して逃れる体制も整備されていたといいます。
米国環境保護庁(EPA)のシステムに虚偽データを入力する役割も担っており、「当時は1週間に25万ドル規模の取引がありました。すべてが虚構で成り立っていた」と振り返りました。
タイムシェア詐欺では、被害者に「物件を売却できる」と持ちかけ、仲介手数料や税金名目で金銭を支払わせる“リロード”型の手法を展開。被害者が一度支払いを済ませた後も、「手続きに追加費用が必要」と再度の支払いを求める悪質な構造が構築されていました。
同氏は、「コールセンターでは、スタッフが泣き叫ぶ被害者に対しても冷酷に電話を切り、別名で再度架電するなどの指示が飛んでいました」と証言。顧客データベースは精緻に管理され、苦情が発生すると会社名や電話番号を変更して逃れる体制も整備されていたといいます。
そのときの心境として、「やめたかった。でも同時に“貧乏にはなりたくない”という思いが抑えられなかった」と吐露し、倫理と現実の狭間で揺れながら、組織と家族の圧力の中で自らの意思を見失っていった過程を印象的に語りました。
ジャリヴ氏は、現在、ウェブ制作とSEOマーケティング事業を展開しており、二児の父として平穏な生活を送っていると述べました。「どういう人とつきあうのかがすべてを決める。過去の私は、反面教師そのものでした」と語り、これからは家族のためにも倫理的な選択をし続けたいと力強く宣言しました。
ジャリヴ氏は、現在、ウェブ制作とSEOマーケティング事業を展開しており、二児の父として平穏な生活を送っていると述べました。「どういう人とつきあうのかがすべてを決める。過去の私は、反面教師そのものでした」と語り、これからは家族のためにも倫理的な選択をし続けたいと力強く宣言しました。

アレックス・ジャリヴ氏とギル会長

アレックス・ジャリヴ氏(スクリーン越しに)
捜査官の視点
一方、元FBI捜査官リチャード・ビースリー氏は、FBIにおいて30年以上のキャリアを持つ元特別捜査官であり、金融犯罪・汚職・医療詐欺など多岐にわたる事件を手がけてきました。特に資産差押え業務や捜査戦略に精通しており、本事件でもジャリヴ氏の行動を精緻に追跡し、法的責任を追及する役割を担いました。
本件について、ビーズリー氏は、2011年にネバダ州でタイムシェア詐欺の噂を耳にし、捜査を開始したと述べました。当初はわずかな手がかりしかなく、関係者の自宅を張り込み、銀行での動向を追うという“足を使う”調査を重ねていったといいます。
やがてカナダ警察、シークレットサービス、EPAとの連携が進み、バイオ燃料詐欺の実態も明るみに出てきました。取引実績や製造量に不審点が多く、「EPAからの通報により、ネバダ州に拠点があることが判明した。事実上、燃料は製造も流通もしていなかった」と証言しました。
捜査の中で、詐欺グループが社名や登記住所を頻繁に変更していたこと、また“姿を消す”タイミングが組織的に管理されていたことなども把握。「ネット上の情報だけでは限界があり、やはり現場に足を運ぶことが重要」と、捜査におけるフィールドワークの意義を強調しました。
また、ビースリー氏は、これまで数多くの被疑者に接してきた経験から、「罪に問われた人物であっても、常に尊厳をもって接するべきである」との信念を示しました。「相手を見下していては、本当の真実にはたどり着けない」との言葉は、調査・監査・法執行に携わる全ての人にとって重く響きました。
一方、元FBI捜査官リチャード・ビースリー氏は、FBIにおいて30年以上のキャリアを持つ元特別捜査官であり、金融犯罪・汚職・医療詐欺など多岐にわたる事件を手がけてきました。特に資産差押え業務や捜査戦略に精通しており、本事件でもジャリヴ氏の行動を精緻に追跡し、法的責任を追及する役割を担いました。
本件について、ビーズリー氏は、2011年にネバダ州でタイムシェア詐欺の噂を耳にし、捜査を開始したと述べました。当初はわずかな手がかりしかなく、関係者の自宅を張り込み、銀行での動向を追うという“足を使う”調査を重ねていったといいます。
やがてカナダ警察、シークレットサービス、EPAとの連携が進み、バイオ燃料詐欺の実態も明るみに出てきました。取引実績や製造量に不審点が多く、「EPAからの通報により、ネバダ州に拠点があることが判明した。事実上、燃料は製造も流通もしていなかった」と証言しました。
捜査の中で、詐欺グループが社名や登記住所を頻繁に変更していたこと、また“姿を消す”タイミングが組織的に管理されていたことなども把握。「ネット上の情報だけでは限界があり、やはり現場に足を運ぶことが重要」と、捜査におけるフィールドワークの意義を強調しました。
また、ビースリー氏は、これまで数多くの被疑者に接してきた経験から、「罪に問われた人物であっても、常に尊厳をもって接するべきである」との信念を示しました。「相手を見下していては、本当の真実にはたどり着けない」との言葉は、調査・監査・法執行に携わる全ての人にとって重く響きました。

リチャード・ビースリー氏
本セッションは、詐欺加害者と捜査官という立場の異なる二人が一堂に会し、不正の構造と人間の弱さ、そして希望を語る貴重な機会となりました。不正は突如として始まるものではなく、小さな逸脱の積み重ねによって形成されるものであること、そして倫理的判断の連続が運命を大きく左右することが、実例として示されました。このような実例から、倫理的リーダーシップと防止施策の策定の重要性を改めて感じました。
(なお、ACFEは本方針として、有罪判決を受けた不正実行者(フロードスター)に対して報酬を支払っていないことを明示しており、本セッションも教育的観点から構成されています)
(なお、ACFEは本方針として、有罪判決を受けた不正実行者(フロードスター)に対して報酬を支払っていないことを明示しており、本セッションも教育的観点から構成されています)
閉会
この対談で、3日間にわたるACFEグローバルカンファレンスは終了しました。ギル会長の「ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。次回のACFEイベントで再びお会いできますことを、心より楽しみにしております」との挨拶で、ついに3日間のメインカンファレンスが終了しました。大きなスーツケースを引きながら足早に去る参加者もいる一方、「ボストンで会いましょう」と別れを惜しむ参加者も多くいました。
数多くの学び、約100人の登壇者、そして、2,000人を超える不正と闘うプロフェッショナルとの出会い、と、この充実した3日間を共に送った参加者は、それぞれ会場を後にしました。
報告者:ACFE JAPAN 事務局





