
理事長対談 第12回:「日本のコーポレートガバナンスの未来」について、オリックス株式会社の宮内 義彦 シニア・チェアマンに聞く
2023年4月3日
ACFE JAPAN岡田理事長「公認不正検査士」インタビュー#2:髙橋康文Miletos社長「不正検出の経費精算システムで企業の“割れ窓”を防ぐ」
2025年7月28日
どうしたら不正は防げるのか――。わが国唯一の不正対策機関、日本公認不正検査士協会(ACFE JAPAN)の岡田譲治理事長(元三井物産副社長CFO=最高財務責任者、元日本監査役協会会長)が、さまざまなビジネスシーンで活躍する公認不正検査士(CFE)のフロントランナーの素顔に迫る本企画。
第1回は、IPO(新規上場)支援会社のタスク(東京・豊島区)のビジネスソリューション事業本部の星多恵さん。タスクの特色は、東京証券取引所で「特別注意銘柄」(特注銘柄、2024年1月に特設注意銘柄から呼称変更)に指定された企業のコンサルティングを担当し、指定解除を目的とした支援事業に乗り出していることだ。星さんは指定解除の業務を経験したあと、現在は部長職としてスタートアップ企業と投資会社を結びつけるつける業務に携わっている。そんな星さんにとってのCFEとは――。
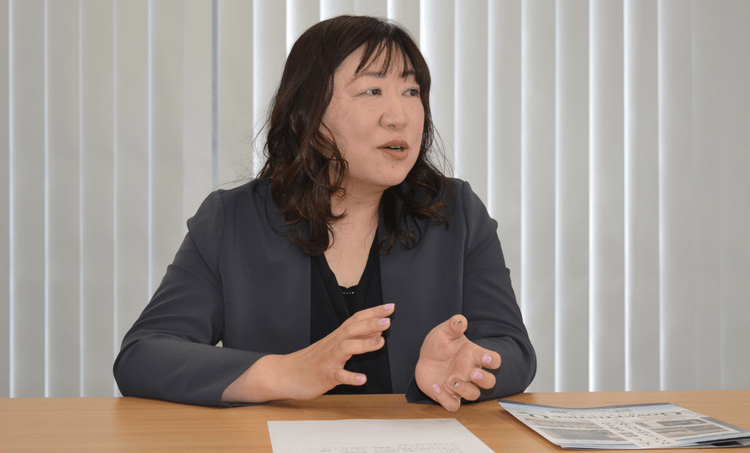
星多恵 氏
株式会社タスク
ビジネスソリューション事業本部
Head of Department
公認不正検査士(CFE)
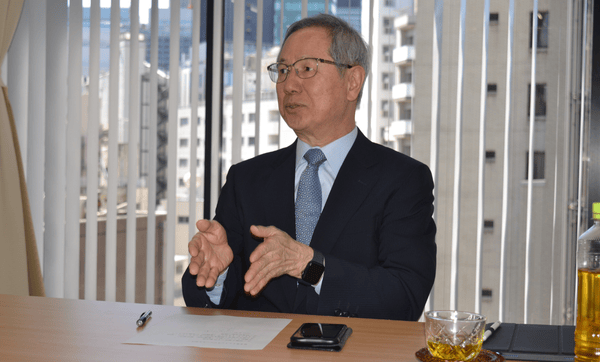
岡田譲治 氏
日本公認不正検査士協会 理事長
横浜国立大学卒業後、74年三井物産入社。2014年代表取締役副社長執行役員CFO(最高財務責任者)、15年6月常勤監査役(~19年6月)、17年11月公益社団法人日本監査役協会会長(~19年11月)。23年6月一般社団法人日本公認不正検査士協会(ACFE JAPAN)理事長
このほか、太陽有限責任監査法人経営評議会委員、日本航空社外監査役、金融庁スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議メンバー、日本取引所自主規制法人外部理事、日本電気社外取締役などを務める。
公認不正検査士(CFE)
特注指定解除に求められる「自社の考え」
上場企業で不正が発覚した場合、東証の判断で上場廃止になる場合があります。ただ、一気呵成に廃止に至ることは少なく、多くは「特別注意銘柄」に指定し、改善状況を見ていくことになります。タスクはこのような特注銘柄になった上場企業を支援しているそうですね。具体的にはどのようなサポートをされるのですか。
ご存じのとおり、特注銘柄に指定されると、1年以内に不祥事の原因究明と再発防止策を記載した「内部管理体制確認書」を東証に提出しなければなりません。確認書は審査にかけられ、これを通過しないと指定は解除してもらえません。不祥事が発覚した会社は内部管理体制に課題を抱えていることが多く、社内規定を一からつくり直し、運用を全面的に見直す必要があります。私たちはこのような内部統制の構築を手助けし、確認書の作成も応援しています。
私は日本取引所グループの自主規制法人の理事を務めています。IPOもさることながら、不祥事を引き起こした上場企業の状況を見聞きすることもありますが、大企業であれば、内部統制をはじめとするコーポレートガバナンスの側面においても、組織や人員を相応に投入して対応できるものです。しかし、上場しているとはいえ、中堅以下の規模になると、内部統制部門がもともと脆弱で、課題を抱える企業も少なくないでしょう。
ただ、卑近な例えですが、人も“退学処分”が目前に迫らないとなかなか勉強しないのと同様、企業も上場廃止が現実問題にならないと、なかなか体制整備には本腰が入らないものではないですか。
そうなんです。制度や仕組みを理解してもらうことも大切ですが、実は、最も難しいのは経営者のマインド(心持ち)を変えることだと思っています。
上場そのものに影響を与えるような深刻な不祥事が起きると、多くの場合、経営トップは交代することになります。ですので、後任のトップには基本的に、不正には直接関わっていない方が就任します。そうなると、社長本人としては、なかなか当事者意識を実感できないものです。
一方で、特注銘柄の指定を解除する過程では、東証の担当者と面談し、さまざまな課題を突き付けられて、精神的にも落ち込みます。私たちはいろいろとアドバイスをしながら、経営者本人に本気になってもらいたいと考えています。「自分自身がこの会社の舵取りをしなければならないのだ」という意識を持ってもらうまで、経験上、だいたい3、4カ月はかかるという印象ですね。
これまでタスクは特注銘柄の解除でどのくらいの会社を支援してきたのですか。また、何か共通して気づいたようなことはありますか。
これまでに支援してきたのは20社以上になります。その中で感じたことは、支援する立場の私たちが前面に出過ぎてはいけないということです。ある企業から、指定解除に向けたプロジェクトの「ファシリテーター(合意形成のリーダー役)」を担ってほしいと言われたことがありました。これについては、やんわりとですが、お断りしました。
なぜかと言うと、コンサルタントの言う通りに仕上げた提出書類はどうしても画一的になってしまう面があります。実際、別の会社なのに、コピー・アンド・ペーストで同じような言い回しになっている提出書類も少なくないようです。実際、東証もそういった観点で提出書類をチェックするようになってきました。やはり、その企業の実情に応じて、自らの考えで自主的に指定解除、そして、再生に向けて取り組んでほしいという考えからです。ですので、私たちも、自分たちの評価を自分たちの言葉で書くようにお願いしています。

実務家の肉声に触れることができるACFEでの活動
星さんはACFE JAPANの中にある研究会でも精力的に活動をしているようですね。
「みんなでつくる不正対応研究会」や「内部通報実務研究会」など4つの研究会に参加させてもらっています。それぞれ原則、リアル、オンラインを問わず月1回のペースで集まっています。講師に実務家や有識者の方を招くため、研究会は学びの場として非常に役に立ちますね。例えば、内部通報では、通報窓口を引き受けている弁護士や、企業の担当者のお話を聞きことができます。
大企業の内部通報にはハラスメント関係のものも多く、場合によっては人事などの腹いせといった内容も含まれるそうです。そういった現実は、やはり、実務に携わっている方から教えてもらうしかありません。大変貴重な機会で、私が経験してこなかったことをたくさん学ぶ機会があります。
内部通報制度には、どうしてもそういう側面はありますね。大きな組織の場合、どうしても個人的な問題やパワハラ、セクハラといった本来、公益通報では受け付けることを想定していない内部通報が相当数混じってしまうものです。実際、こうした内容に直に対応する職員が疲弊し、ノイローゼになってしまうケースもあるようです。
ただし、だからと言って、内部通報制度の運用を疎かにしては、本当に検出すべき不正自体を見逃してしまいます。現場にとっては大変なことですが、通報に真摯に向き合い続ける必要があります。私は、このように内部通報に携わる人にこそ、CFE(公認不正検査士)の資格を勧めたい。
そもそも、不正に対応するためには、論理、倫理、心理、この3つ「理」が大切ではないでしょうか。
おっしゃるとおりです。私はその中で、特に「心理」に着目すべきではないかと思っています。以前、人事部門を担当していたとき、メンタルに変調をきたして休職する人に会社としてどう接したらよいのか、常に悩んでいました。
人それぞれで状況が違うため、これは永遠の課題と言える問題です。本人の言っていることを否定すると症状が悪化します。また、休職期間は多くの企業において勤続年数で決まっていますが、必ずしもその期間内で回復するとは限りません。だからといって、期間が過ぎたからといって、機械的に「退職してください」とも言えない。やはり、人の心理を学んで対応するしかありません。
これは不正対応の現場でも同様で、通報者、あるいは被害者の心理状態を考慮しながら、事態を前に進めていくしか解決策はないのではないでしょうか。
最近、大きな問題となった大企業のケースで言えば、「そのうち本人(被害者)が笑顔になるじゃないの」といった企業内での対応も問題視されました。人の心理を分かる、分かろうとする人がいれば、また、違っていたでしょうね。
私は以前、別の会社で経理部門を担当していたことがありました。CFEになった今、さまざまな企業の不正や不祥事に関する調査報告書を読む機会がありますが、経理部門が何のエビデンス(証拠)もなく、上層部から言われた金額をシステムにそのまま入力し、それが不正に発展しているようなケースを見かけることがあります。
不正会計を防ぐうえで、経理の仕訳入力は最後の砦ですよね。本来、経理担当者は、誰が何を言おうと、裏付けのない金額を入力してはいけないものです。少なくとも、私はそのように教わりました。私の経験ですが、売り上げを入力したのに入金されないことがあり、担当の管理職に問い合わせると、「あ、あれは(事業が)なくなったから」と言われて唖然としたことがあります。
理想論に聞こえるかもしれませんが、エビデンスがないものについては、担当者レベルで抵抗するしかありません。もしかしたら、1年目、2年目といった経験の浅い経理担当者が、上から言われて、やむを得ず入力しているのかもしれませんが、それは結果的に会計不正の一端を担わされていることにほかなりません。自分だったらと考えると、いたたまれなくなってしまいます。
経理を大切にしない会社はいずれダメになります。私も経理部門が長いので、その点、よく分かります。ところで、CFEになったきっかけ、そしてACFE JAPANに望まれることはありますか。

正直言うと、会員になるまでCFEのことはまったく知りませんでした(苦笑)。現在の仕事に就いて弁護士や公認会計士の方々と名刺を交換した際、「公認不正検査士」と書いてあることから興味を持ったのが、入会のきっかけです。ACFEに入ったお陰で、ネットワークを広げることができました。
要望というほどのことでもありませんが、年に1度のカンファレンス(年次総会)を含めて、ベテランの弁護士や会計士の方だけでなく、中堅や若手の現場に近い実務担当者のトークセッションなどがあれば、私のような立場の人間にはとても参考になるのでは、と思いますね。特に不正調査を実施される第三者委員の苦労話などをお聞きしたいです。
やはり、教科書とは違った“生の声”に触れる機会、それがACFEの強みだと思います。
そういう“場”の提供こそ、ACFEの役割でしょう。本日は貴重なお話をありがとうございました。



