36th ACFE Global Conference : 3日目
2025年6月27日ACFE JAPAN20周年記念 カンファレンス 開催レポート
2025年11月11日
第36回ACFEグローバルカンファレンス総括
第36回ACFEグローバルカンファレンスは、ACFE(Association of Certified Fraud Examiners)本部が主催する年次最大規模の不正対策専門家向け国際会議であり、2025年6月22日(日)から27日(金)(日本時間)まで、テネシー州ナッシュビルで開催されました。今回はナッシュビル中心街のミュージック・シティ・センターをメイン会場とし、対面とオンラインのハイブリッド形式で実施され、計5,465人が参加しました。
本カンファレンスの全体テーマは「トレイルブレイザー(先駆者、開拓者)」とされ、参加者には「現状維持に満足せず、変化を起こそうとする者たち」として、不正対策における知識や手法の習得だけでなく、「真実と説明責任に情熱を持つ者同士のつながり」の重要性が強調されました。
今回のACFEグローバルカンファレンスでは、進化し続ける不正の脅威に対し、専門家がいかに「先駆者」として立ち向かうべきか、多角的な視点から議論が交わされた3日間となりました。AIやデータ分析、OSINTといった最新テクノロジーの活用が、不正検知・調査の最前線において不可欠であることが繰り返し強調されました。同時に、内部告発者保護の重要性、人質交渉術に学ぶコミュニケーションの心理、詐欺師の巧妙な手口と被害者心理、そして不正実行者の生の声から学ぶ組織的腐敗の構造といった「人間の要素」への深い洞察も提供されました。
本カンファレンスは、知識やスキルの習得だけでなく、世界中の不正対策のプロフェッショナルが結束し、互いの知見を共有し、協力体制を強化する貴重な機会となりました。
各日詳細レポート:ACFE JAPAN 事務局
1日目 2日目 3日目


カンファレンスの各日程の主なハイライトは下記の通りです。
■不正被害の規模と新たな脅威:CEOのジョン・ウォーレン氏は、世界で年間約5兆ドルの不正損失があり、「もし“詐欺”が国であれば、世界で5番目に大きな経済規模を持つ国になっているかもしれない」と警鐘を鳴らしました。また、国家レベルのハッカーや国際的犯罪組織、AIを用いたディープフェイクといった「全く新しい脅威」に組織がさらされていることを指摘しました。
■クレッシー賞受賞者基調講演:ACFE最高栄誉である「クレッシー賞」は、世界貿易機関(WTO)事務局長であり、元ナイジェリア財務大臣でもあるンゴジ・オコンジョ=イウェアラ博士に贈られました。彼女は、他者の犠牲の上に個人の利益を得る「腐敗」を、経済・社会・開発全体をむしばむ「構造的脅威」と定義し、ナイジェリアでの架空職員排除や燃料補助金詐欺阻止の経験を共有しました。テクノロジーによる業務のデジタル化が不正削減に直結すると強調し、「変革はあなたから始まる」と参加者に力強いメッセージを送りました。
■分科会(ChatGPTの活用):「限りない可能性―ChatGPTを活用したプロフェッショナルの成長と影響力の拡大」と題したセッションでは、ChatGPTがキャリア形成、戦略立案、不正調査、業務効率化などの様々な場面で補助ツールとして活用できる可能性が示されました。
■マリナ・ウォーカー・ゲバラ氏基調講演:国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)の元副ディレクターであり、パナマ文書やパラダイス文書の調査を主導したマリナ・ウォーカー・ゲバラ氏が登壇しました。彼女は、複雑化した国際的な不正に対抗するためには、単独ではなく「信頼に基づく国際協働」と「テクノロジーの活用」が不可欠であると強調しました。特にAIや機械学習が、膨大な非構造化データの分析や複雑な関係性の可視化に役立つと述べ、「見えないものを見ようとする“ブラックホール科学者”である皆さんは、民主主義を再構築する道具であるべきだ」と語りました。
1日目:2025年6月23日(月)
■オープニング・ジェネラル・セッション:ACFE本部バイスプレジデントのロス・プライ氏が開会の挨拶を行い、ジョン・ギル会長が2026年6月から新しいCFE試験が始まることを発表しました。新試験は現代の不正検査士に求められる知識とスキルに対応するよう、構成・出題内容ともに刷新される予定です。■不正被害の規模と新たな脅威:CEOのジョン・ウォーレン氏は、世界で年間約5兆ドルの不正損失があり、「もし“詐欺”が国であれば、世界で5番目に大きな経済規模を持つ国になっているかもしれない」と警鐘を鳴らしました。また、国家レベルのハッカーや国際的犯罪組織、AIを用いたディープフェイクといった「全く新しい脅威」に組織がさらされていることを指摘しました。
■クレッシー賞受賞者基調講演:ACFE最高栄誉である「クレッシー賞」は、世界貿易機関(WTO)事務局長であり、元ナイジェリア財務大臣でもあるンゴジ・オコンジョ=イウェアラ博士に贈られました。彼女は、他者の犠牲の上に個人の利益を得る「腐敗」を、経済・社会・開発全体をむしばむ「構造的脅威」と定義し、ナイジェリアでの架空職員排除や燃料補助金詐欺阻止の経験を共有しました。テクノロジーによる業務のデジタル化が不正削減に直結すると強調し、「変革はあなたから始まる」と参加者に力強いメッセージを送りました。
■分科会(ChatGPTの活用):「限りない可能性―ChatGPTを活用したプロフェッショナルの成長と影響力の拡大」と題したセッションでは、ChatGPTがキャリア形成、戦略立案、不正調査、業務効率化などの様々な場面で補助ツールとして活用できる可能性が示されました。
■マリナ・ウォーカー・ゲバラ氏基調講演:国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)の元副ディレクターであり、パナマ文書やパラダイス文書の調査を主導したマリナ・ウォーカー・ゲバラ氏が登壇しました。彼女は、複雑化した国際的な不正に対抗するためには、単独ではなく「信頼に基づく国際協働」と「テクノロジーの活用」が不可欠であると強調しました。特にAIや機械学習が、膨大な非構造化データの分析や複雑な関係性の可視化に役立つと述べ、「見えないものを見ようとする“ブラックホール科学者”である皆さんは、民主主義を再構築する道具であるべきだ」と語りました。



2日目:2025年6月24日(火)
■出展ブースの様子:スポンサー企業だけでなく、FBI、警察、自治体などの政府機関も不正対策の出展をしていました。特にU.S. Postal Inspection Service(USPIS)は、アメリカ最古の連邦法執行機関であり、郵便詐欺の取り締まりを通じて、ポンジ・スキーム、公的汚職、保険詐欺など多くのホワイトカラー犯罪を摘発してきたことが紹介されました。■トム・ディバイン氏基調講演:不正事件の解決への貢献者に贈られる「センチネル賞」を受賞したトム・ディバイン氏が登壇しました。彼は通報者を「公的信頼を裏切る権力の濫用に対して、自由な言論によって立ち向かう者」と定義し、通報者保護制度の強化の必要性を訴えました。
■クリス・ヴォス氏基調講演:元FBI国際人質交渉人であるクリス・ヴォス氏が、「人間の本能に基づいた交渉術」について講演しました。彼は、相手に「Yes」を引き出すことではなく、「Noを言える環境づくり」が信頼関係を築き、本音を引き出す上で重要であると述べました。これを「戦術的共感(Tactical Empathy)」と呼び、日常のコミュニケーションにも応用可能であると説明しました。
■AIによる不正検知:分科会では、AI技術を活用した次世代型不正検知手法が紹介されました。AIはリアルタイムでの異常検知、パターン分析、リスクスコアリングにおいて、従来手法に比べ柔軟性・精度・スケーラビリティ・自己学習性で優れていると強調されました。クイックペイ社の事例では、AI導入により従来見逃していた少額資金流用などを早期検知し、検知スピード向上や人的リソース削減に繋がったことが報告されました。
■レイシー・モズリー氏基調講演:人気ポッドキャスト「Scam Goddess」のホストであるレイシー・モズリー氏が、詐欺師の心理的トリックや「語りの技術」についてユーモアを交えて解説しました。彼女は、被害者は「判断が甘い人」ではなく「日常の中で一瞬の判断を強いられる状況に置かれた人」であるとし、詐欺行為の本質が「必要性」や「孤独」につけこむことにあると訴えました。
■不正調査の将来(コンテクスチュアル・インベスティゲーション):クオンテクサ社のリッキー・ D・スルーダー氏は、現代の複雑な不正スキームに対して、「つながる文脈(connected context)」を活用した新しい調査手法を提唱しました。「エンティティ・リゾリューション」と「グラフ分析」により、サイロ化されたデータや断片的なアラートではなく、人物や組織、取引などのネットワーク構造から不正を検出する有効性が示されました。
■OSINT(オープンソース・インテリジェンス):米国大手保険会社のアンソニー・リーゼック氏は、SNSや検索エンジンなど公開情報を収集・分析するOSINTの活用法をライブデモを交えて紹介しました。彼は、「技術の導入そのものではなく、“公開情報をつなぐ目と考察力”こそ調査者の価値である」と述べました。

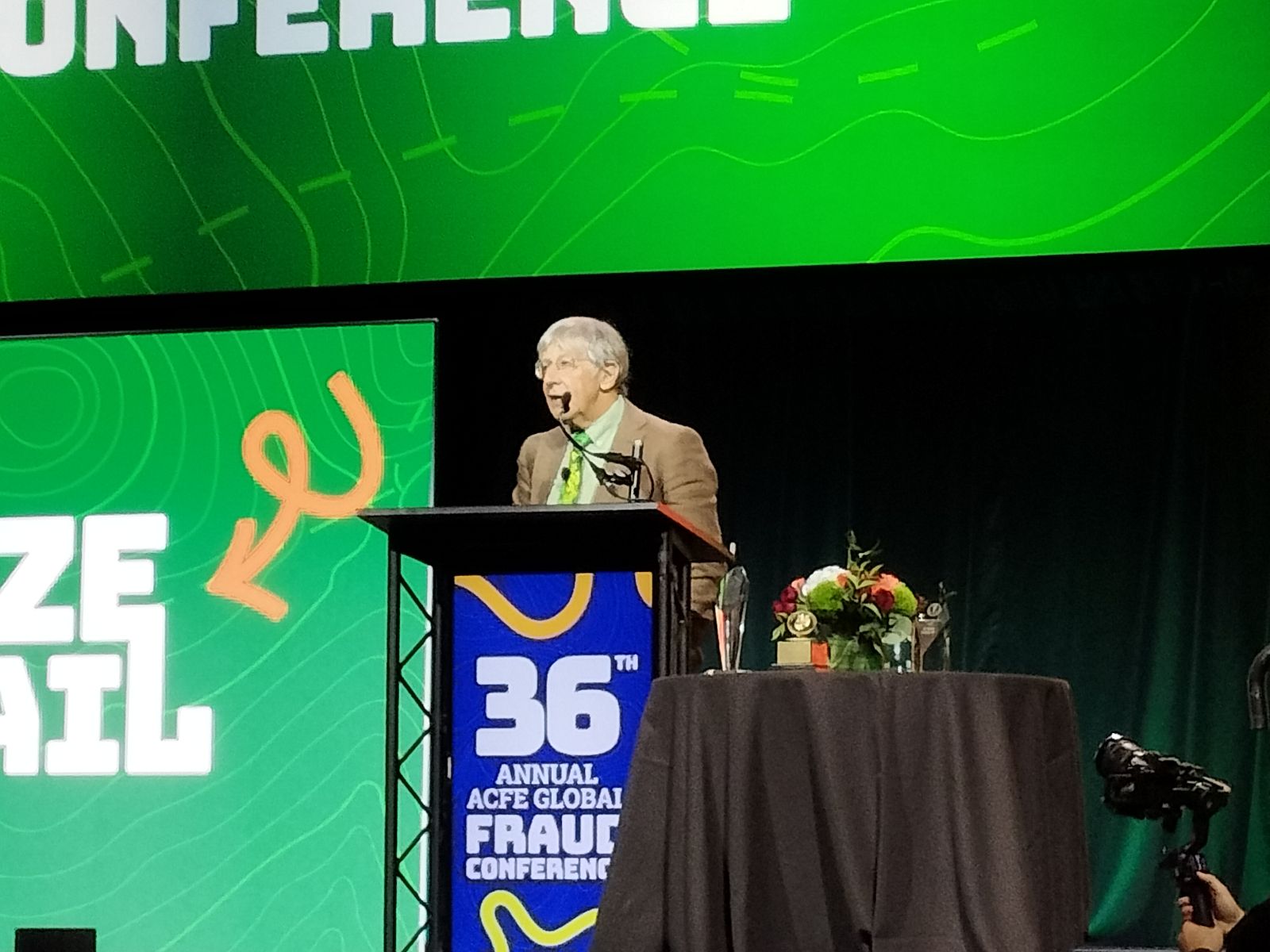

3日目:2025年6月25日(水)
■元フロードスターによるセッション:本カンファレンス最終日には、極めて異色かつ示唆に富むセッションが行われました。■ウォルト・パブロ氏(元MCI/ワールドコムの不正実行者)が、ACFE会長ジョン・ギル氏とのインタビュー形式で登壇しました。彼は、会社の急成長と成果至上主義、倫理的リーダーシップの不在が、いかにして社員の倫理的判断を鈍らせ、「暗黙の了解」として不正が許容される空気を醸成したかを赤裸々に語りました。現在の活動として、受刑者支援を行うコンサルティング会社「Prisonology」を経営していることが紹介されました。
■アレックス・ジャリヴ氏(国際的な詐欺事件に関与し有罪判決)と、その事件の捜査を主導した元FBI特別捜査官リチャード・ビーズリー氏が、加害者と捜査官それぞれの視点から対談しました23。ジャリヴ氏は、バイオディーゼル詐欺やタイムシェア詐欺の手口を明かし、「貧乏にはなりたくない」という思いと組織の圧力の中で自らの意思を見失った過程を語りました。ビーズリー氏は、捜査における「現場に足を運ぶことの重要性」と、「罪に問われた人物であっても、常に尊厳をもって接するべき」という信念を強調しました。
■これらのセッションは、不正が個人の倫理観の欠如だけでなく、組織的な腐敗、企業文化、そして小さな逸脱の積み重ねによって形成されるものであることを浮き彫りにし、倫理的リーダーシップと防止施策の重要性を改めて示唆する内容でした。





